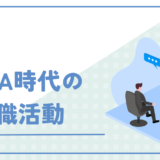こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。
2023年1月17日に経団連(日本経済団体連合会)により「2022年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」が公表されています。
特徴は、日本を代表する企業群の労務担当役員(経営側の人事責任者)が対象の調査ということです。こうしたデータから企業経営のトレンドを掴んでおくことは、就活・転職の際の企業研究においても役立ちます。会社の本質を見抜くためにも。
前回に引き続き、調査結果の中から、ポイントになるデータを一部引用し、分析してみます。あくまでも私見ですので、その点はご容赦ください。
 2022年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果(経団連)から日本企業の人事労務の方向性(トレンド)を確認しておきましょう!:パート①
2022年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果(経団連)から日本企業の人事労務の方向性(トレンド)を確認しておきましょう!:パート①
2022年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果
新型コロナの影響で拡大した在宅勤務などのテレワークについて、労務担当役員等がどのような方針を定めて実行していくのか。これにより、その企業が求める「働き方の本質」が見えてきます。
・部門・職種の特性等に応じて、各社員がテレワークと出社を選択できる働き方を推進していく 68.4%
・オフィスや現場等への出社を基本とする 17.4%
・今後、方針を検討する(未定を含む)5.6%
・その他(「個々人の生産性や状況により判断」などがあった等) 5.1%
・テレワークを中心とした働き方を推進していく 3.5%
ポイントは、「これから方針を決める、未定が少なく」、方針が定まっている点。そして、企業主導で「テレワークを中心とした働き方を推進していく」「オフィスや現場等への出社を基本とする」と決めるのではなく、「社員がテレワークと出社を選択できる働き方を推進していく」が7割近くを占めること。これからの働き方のトレンドです。
経営者にとってもこれは、事業継続(事業継続計画:BCP)を考えるうえで必要な施策でもあります。
地震などの自然災害、テロ、戦争、感染病等、いつ何が起きるか分からない VUCA時代に(過去からは予想もできないことが起きている今)、いつ・何が起きても、従業員の安全を確保しながら、事業を継続、または早期に復帰していくことは重要なリスクマネジメントです。経営トップに危機管理能力と判断し行動する能力があれば、然るべき人事方針・人事施策を定め、従業員と意思統一しているはずです。
これは、これからの会社選びで最も重要なことかもしれません。生きていくうえでも。
・実施していない 32.8%
・一定の進捗がみられる 29.0%
・あまり進捗がみられない 18.6%
・進捗があるがわからない(把握していない)7.6%
・進捗がみられない 6.6%
・明確に進捗が見られる 5.5%
テレワークの一番の課題は、現場業務にあります。この現場のリモート化を実現する対策のひとつにDX化があります。その企業のDXへの取り組み姿勢、意欲がここに繋がってきます。そうした意味においても、企業のDXに対する取り組み状況は、働き方(結果としての生産性向上)にも大きな影響を及ぼします。
DXの取り組みも会社選びで注目すべき重要なポイントです。(調査結果は、パート①で解説)
 2022年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果(経団連)から日本企業の人事労務の方向性(トレンド)を確認しておきましょう!:パート①
2022年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果(経団連)から日本企業の人事労務の方向性(トレンド)を確認しておきましょう!:パート①
法律で定められた65歳までの雇用確保措置について、実施している措置の調査データがこちら。
・65歳までの継続雇用制度の導入 81.1%
・65歳までの定年引上げ 18.4%
・定年廃止 0.5%
厚生労働省の調査とほぼ同様に、8割強の大多数の企業は、60歳定年制で65歳までは有期雇用労働者としての継続雇用(再雇用)制度を導入しています。
「65歳までの継続雇用制度」を導入している企業における「定年引上げ・廃止」の導入予定の有無についての調査では以下のような結果となっています。
・導入予定なし 80.1%
・導入予定あり 19.9%
まだまだ、能力よりも年齢で人(人材)を評価している労務担当役員等が多いのが実情です。日本型雇用システムからの脱却が程遠いようで・・・。
また、これも「非正規労働者」が増える要因のひとつでもあるわけです。
参考までに、法律で努力義務とされた「70歳までの高齢者就業確保措置」の対応状況についての調査結果です。
・対応する予定である 34.6%
・対応を検討中である 25.7%
・対応済みである(決定済みであるを含む)22.8%
・検討していない(検討予定なしを含む)16.9%
これが日本の労務担当役員等の残念な結果の現れです。
義務規定は、やらないと罰則があるからやる。努力義務は、やらなくても罰則がないから指導されるまで(義務化されるまで)はやらない。というなんとも分かりやすく判断。こういう企業で従業員エンゲージメントなど上がるはずはありませんよね。というより、従業員エンゲージメントには興味・関心はないでしょうね。
60歳から64歳までの社員のモチベーションを維持・向上させるための取り組みについての調査データです。
① 人事評価の実施 79.8%
② 賞与・一時金の支給 71.4%
③ 勤務時間・日数など柔軟な勤務制度の適用 55.2%
④ 基本給水準の引き上げ 36.7%
⑤ 従事する職務の見直し 34.4%
これは、65歳までの継続雇用制度の導入 81.1% という結果がそのまま影響していると考えられます。
継続雇用制度の多くは、60歳定年でいったん退職扱いとし、新たに有期雇用契約の締結により雇用継続する「再雇用制度」を採用する企業が多数です。定年後の再雇用であっても期間の定めのある有期雇用労働者になりますので、パートタイマーや契約社員の有期雇用労働者と同様、パートタイム労働法・第9条が適用されます。短時間労働者とありますが、期間の定めのあるフルタイム労働者も同様に解されています。
第9条(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)
事業主は、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(以下「職務内容同一短時間労働者」という。)であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(以下「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。
2 前項の期間の定めのない労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとする。
同一労働同一賃金の原則が問われます。したがって、モチベーションを維持・向上というより、法の趣旨に反しないように取り組んでいる可能性が高いとも思われます。
例えば、「勤務時間・日数など柔軟な勤務制度の適用 55.2%」とありますが、これを通常労働者との責任の程度の違いとして、賃金等に大きな差を設ける場合もありますので。
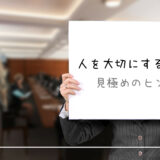 人を大切にする会社か?見極めのヒントとコツ 〜高年齢者確保措置について ①雇用のリスク〜
人を大切にする会社か?見極めのヒントとコツ 〜高年齢者確保措置について ①雇用のリスク〜
学校教育からいったん離れたあとも、それぞれのタイミングで学び直し、仕事で求められる能力を磨き続けていくことがますます重要になっており、このための社会人の学びをリカレント教育と呼んでいます。(リカレント教育ー厚生労働省)
日本経済再生のために、政府も予算化し、重点課題として積極的に取り組んでいるテーマです。
リカレント教育等の実施状況は以下のとおりです。
・実施している 65.1%
・実施を検討中 16.9%
・現在は実施しておらず、今後も実施する意向はない 18.0%
※本調査において「リカレント・リスキリング教育」は以下と定義
①社員が自身のキャリアアップやキャリアチェンジのためにスキルや専門性を高めるべく、大学等の外部機関で学ぶもの
②企業が人材成長戦略や競争力強化の一環として、社員を大学等の外部組織に派遣し、スキルや専門性の向上を目指すもの
③社員がスキルや専門性の向上を目指し、自社及び自社グループで提供されるプログラム等を受講するもの
いかがでしょう、皆さんの勤め先での実施状況は。
以前とは違い、これを「自己啓発」として労働者の個人的な問題としてとらえる企業より、企業の成長戦略・従業員のキャリア形成の両立としてとらえ、労働時間や有休の休暇扱いでリカレント教育を実施したり、費用を会社が負担したりと、人の成長に対する投資に力を入れる企業が増えています。(国の助成金も増えている背景もありますが)
人材に投資をする・しないで、格差が生じる時代です。会社の将来性を見極めるうえで重要なポイントです。
導入している採用方法(複数回答/あてはまるものすべて)は以下のとおりです。
・職種別・コース別採用 67.2%
・カムバック採用 64.5%
・リファラル採用 62.5%
・その他 6.9%
・経験者採用を行っていない 0.6%
※「その他」の回答としては、「ダイレクトリクルーティング」「個別処遇の嘱託採用」「第二新卒採用」など
今後の方向性で、採用割合を増やすとした採用方法は、「リファラル採用」がトップでした。
リファラル採用とは、自社で働いている従業員からの紹介(推薦)で実施する採用手法のことです。リファラル採用は、従業員エンゲージメント(自社に対する信頼)が高くないと上手く機能しません。反対に、従業員エンゲージメントが低い場合は、クチコミサイトの書き込みなどで、採用活動に悪影響を及ぼしてしまいます。
すべてにおいて、従業員エンゲージメント(自社に対する信頼)が経営にインパクトを与える時代です。そこを、労務担当役員等が理解し、反応しているか。皆さんの勤め先はいかがでしょう。クチコミサイトが荒れ放題になっていませんか?
最後に、新卒採用における学修履歴(成績証明書等)の扱いの調査データです。
・やや重視している 57.0%
・あまり重視していない 29.0%
・重視していない 9.0%
・非常に重視している 4.9%
雇用主側の責任者の労務担当役員等が「非常に重視している」のは、たった 4.9%です。これは、さらに深堀の調査結果があると良かったのですが、残念ながら・・・
逆に、労務担当役員等の経営側の立場にある人たち(人事労務担当者ではなく)が、新卒者に何を期待しているのか、大変興味のあるところです。求める人材の肝でもありますので。
学生の皆さんは、就活で確認すべき重要なポイントです。人事採用担当に「御社が新卒者に期待すること、求めることは何ですか?」と。これが、役員面接や最終選考等での合否に大きく影響するところです。いわゆる「ガクチカ」とも関係してきますので。
これを、明確に答えられない、求める人材像について明確に情報開示できない企業は、ポリシー(方針)がないか、経営層と人事担当者の情報共有がない(コミュニケーションが欠落)、または、人事担当者のエンゲージメントが低いので仕事への意欲が低い、誰でもいいので数を採用しないといけない・・・。いずれにしても、職場の雰囲気に難ありと想像できる企業です。要注意です。
 就活の鉄板「ガクチカ」について違和感を感じるこの頃
就活の鉄板「ガクチカ」について違和感を感じるこの頃
以上、引用は「一般社団法人 日本経済団体連合会 公式サイト」http://www.keidanren.or.jp/