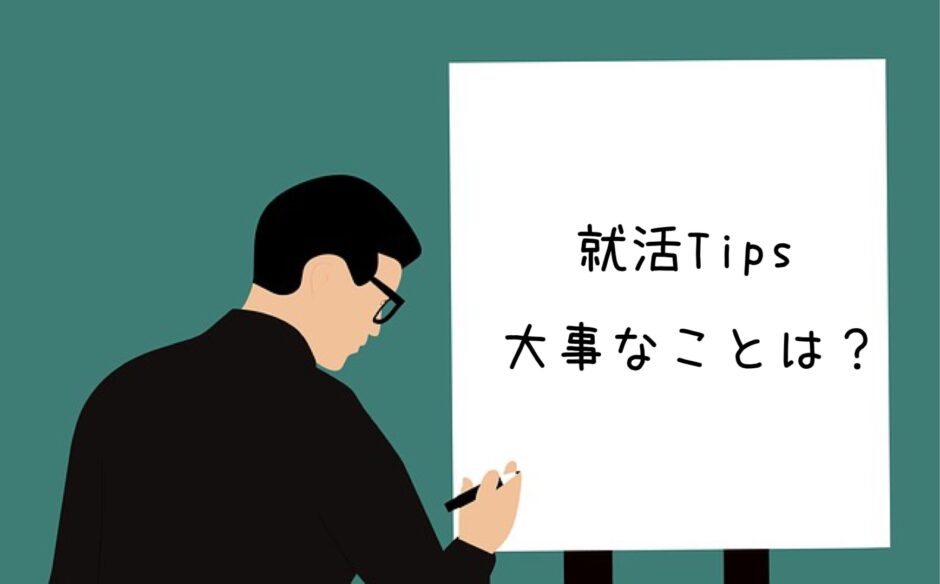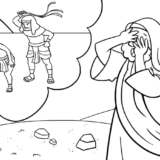こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。
ひと昔前に比べると格段にその機能がアップしているのが学校のキャリアセンター。
国公立と私立の差、学校ごとにも差はありますが、かなり有用なキャリアセンターが増えています。
また、ここ数年、学校対策に力を入れている企業も見られます。
学校ごとの特徴を分析し、求めるタイプの人材を育成している学校としっかり情報交換し、繋がりを大事にしながら、自社に必要な人材を効率よく確実に採用する。
戦略的な攻めの採用のひとつとして、学校との連携強化が見直されているのです。
就職情報サイトに大量のお金をつぎ込んで、むやみやたらにエントリーを集めて絞り込む採用活動の終焉でしょうか。
デジタルな採用とアナログ重視の採用活動のバランス。
バーチャルで、イメージ浸透型の採用は、早期退職の原因を生み出していたひとつの原因でもあります。
現実理解型の採用活動が学生の側からも、企業の側からも、学校からも必要とされています。
本来あるべき採用の姿に戻りつつあるのかもしれません。す

(1) 学生に知名度のない優良企業の発掘
B to B でビジネスを行う優良企業の中には、残念ながら知名度がなく、採用活動が上手くいかないところも多々あります。
そうした企業の中には、ネットで幅広く募集するよりも効率を重視し、学校との繋がりで採用ターゲット校にピンポイントで求人をして採用する、というところがあります。
また、就職指導に力を入れている学校は、積極的に求人の開拓を行い、就職ナビサイトでは目立たないが、OBOGが活躍する優良企業のホットな求人情報を持っています。
(2) 予想外にトントン拍子に進むことも
「こういう学生がいたらぜひ紹介して欲しい!」
「御社のような仕事に興味を持っているこんな学生がいますが、どうでしょう?」
キャリアセンターと採用担当のコミュニケーションが、かなり具体的に進む事も珍しくありません。
話しが具体的な分、マッチングの可能性も高いですし、スピード感も違います。
また、ネット上では採用終了となっていても、キャリアセンターとその企業の採用担当との繋がりが強い場合「では、とりあえず一度その学生と会ってみましょうか」と話しが進むことも。
ちょっとした相談が、予想外に大きく進展することもあるのです。
(3) 現実を実感できる
そもそも、同じ学校の先輩たちはどういう企業に就職し、募集はあっても、どういうところへの就職は難しいのか。
あらかじめ知っておくことも大切です。
多くのキャリアセンターには、先輩たちの就職活動記録が企業ごとにファイリングされていたり、データ化されていたりで「A社へ就職したが○○だから退職した。」など、先輩を通じて企業の裏話や生の声(本音)が聞けたりします。
ネットの掲示板などよりも信頼できる情報があります。
ブラック企業情報、求人詐欺に関する情報はとくに。
最近のキャリアセンターには、様々な業界の民間企業出身の方、人事経験のある方、就職情報会社から転職した方もいらっしゃいます。
広い視野と視点から、社会人の先輩としてのアドバイスや貴重な助言も大いに期待できます。
さらに、キャリア・アドバイザーやカウンセラーなど専門スタッフを配置し、かなり手厚いサービスを提供しているところもあります。
少子化の中、大学や専門学校は生き残りをかけた厳しい状況下にあります。
存続のために、いかに入学者を増やすか。
入学者の募集には、就職の実績が極めて大きな意味を持ちます。
学校にとっても学生の就活結果は重要なのです。
学校も必死です。
また、職業安定法によりハローワークと同様に学校は職業紹介ができますし、職業紹介に努力しないといけないともされています。
卒業後の職業紹介に力を入れている学校もあります。
相談に行けば、しっかりサポートしてもらえるはずです。
履歴書やESの添削、面接の練習なども。
以上、一部ではありますが、キャリアセンター活用のメリットをあげてみました。
学生にとっても(企業にとっても)、キャリアセンターを利用しない手はないですね。
もちろん、無料(職業紹介)ですし。