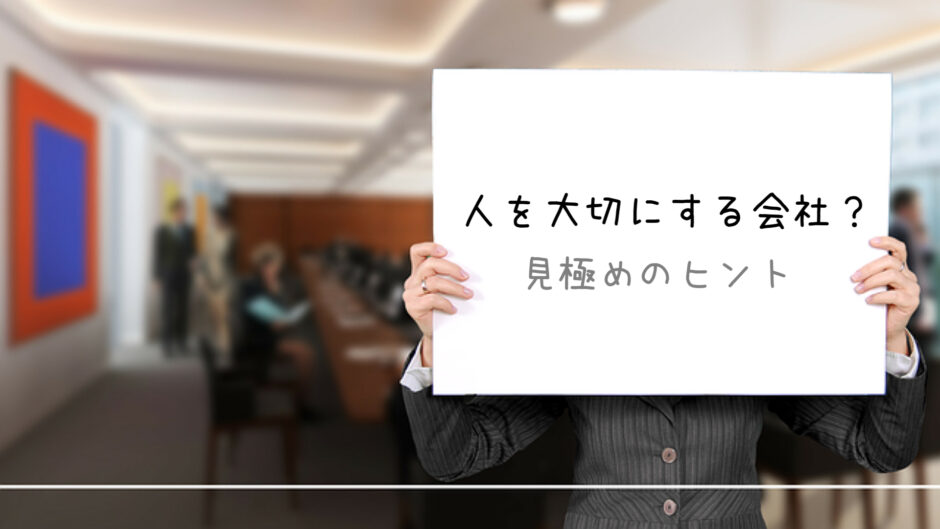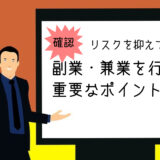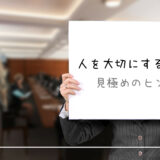こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。
「当社は人を大切にする会社です!」「社員は財産です!」と声高らかに話す経営者、実に多いです。でも、これはごくごく当たり前のこと。当たり前のことをあえて強調して言うことのほうが、むしろ胡散臭く(ブラックぽく)感じますよね。
企業経営において重要な、ヒト・モノ・カネ・情報(4大経営資源)。その中でも、モノ・カネ・情報を活用するのがヒト(人材)。そう、すべてはヒト(人材)次第。ヒト(人材)の確保、育成、成長、活躍(価値創出・働きがい)の好サイクルが、いつの時代も企業経営の基本です。
そして、ヒト(人材)には「感情」があります。経営のポイントはそこにあります。
お金も愛情も人材も、心から集めたいという人に集まってくる。
そしてそれを大切にしてくれる人のところに集まる。
松下幸之助
本当に人材を大切にする会社かどうかは、自社の規定や制度の内容を見るとわかりやすいですよ。
例えば、改正頻度の多い改正育児介護休業法による「育児休業制度」。
妊娠・出産・子育てなど、仕事と育児を両立するうえで重要な法律ですが、これに対する経営層の意識差には、いまだに大きな隔たりがあります。
とくに昭和の時代「24時間戦えますか」の栄養ドリンクのCMのように、家庭を顧みずに働いてきた世代の中には、ワーク・ライフ・バランスに理解のない、化石的な思想の経営者、管理職が存在します。
よって、法規制がないとなかなか進まないのが子育て支援策の実態。
2022年4月1日の法改正で、雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が義務化されました。
◎ 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休(2022年10月1日以降)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。※複数の措置を講じることが望ましいです。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
この「育児休業を取得しやすい雇用環境の整備」の取り組み内容でわかります。本当に人を大切にする経営者なのかどうかが。
法令では、①から④の中から1つ以上の措置を講じれば良しとしています。
働く人の多様な事情よりも、会社の体裁を考える経営者は単純です。
「どれかひとつ、簡単にできるものを選べばいいんじゃない」と。
また、よくあるのは「法令違反にならないように考えて」と、人事担当者や顧問社労士に任せておしまい。
というネガティブなアクション。
でも、法令にはきちん明記してあります。
「事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。」と。
あえて「事業主は」とあるのは、経営トップによる強いメッセージがないと、こうした制度は機能しないということを明らかにしているのです。
とくに、育児や介護休業法に定める各種制度は、上司や周囲の理解と協力が必要不可欠です。
トップダウンのメッセージがないと進みません。
これは、パワハラ、セクハラ、マタハラなどハラスメント防止と一緒です。
これを熟知し、行動に移す(本当に働く人を大切に考える)経営者は、自ずと④の方針の周知を実行しています。
いや、すでに経営方針の重要な人事ポリシーとして周知しているところもあります。
ポジティブに。
なので、人材を大切にするという発想のないネガティブな企業(経営者)は、②の相談窓口の設置のみを選ぶでしょうね。
①と③は手間がかかりますし、そもそも③は育児休業の実績がないとできませんので。
誰もが働きやすい職場づくりを目指すのであれば、複数選択し実施すること(本来、①~④の全部実行)が、むしろ当然とも思える内容になっていますし。
そもそも、2022年4月1日以降に①~④のどれもなにもしていない場合は、明らかな法令違反です。
さて、みなさんの勤め先はどうですか? 経営者がふだん言っていることと実態(アクション)がともなっていますか?
経営者の考え・方針(人か、金か、経営者が何を大切にするのか)は、その会社の規則や制度に滲み出てきます。
その意味合い(どうしてそうなっているのかな?)を見極めると、人を大切にする会社(経営者)かどうかがハッキリします。
客観的な視点で、あらためて勤め先の規則や制度、ルールがどうなっているのか、点検してみてはいかがでしょうか。
(参考)
2022年10月1日の育児介護休業法の改正では、産後パパ育休という新たな制度が始まります。
育児休業の分割取得も可能になるなど、大きくルールが変わります。
4月改正とは違い、10月の法改正では規定の改定と周知が必要になります。要確認ですよ。