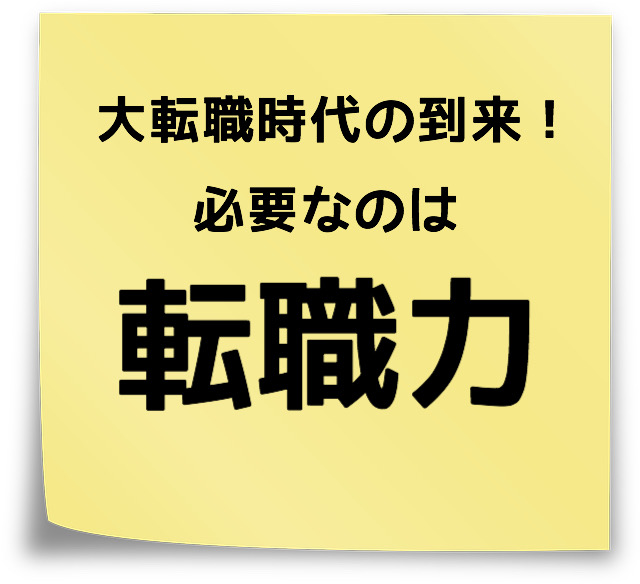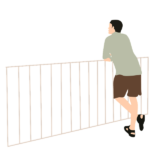こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。
育児休業や介護休業、病気療養の休職、フルタイム勤務が困難な社員などなど、いろいろ訳あってフルに働くことができない従業員が増え、在籍従業員の数に変化はないけど、実働数が減ってしまっているというお困りごと。
そこに、働き方改革。
残業時間の制限や有給休暇の取得義務化で総労働時間が減ってしまい、従来の仕事量がこなせない。
もちろん、従来が過重な労働であったのであれば、従業員の健康を第一優先にして業務調整をしないと、それはそれで絶対ダメなことですが、会社の存続と従業員の生活を考えると、簡単に仕事量を減らすこともできないというお困りごと。
キツキツの仕事で、生産性向上どころか、職場全体がピリピリのイライラ、どよーんと疲弊感も漂い、ハラスメントやメンタル不調の心配も。(そんな実態を予測してかのような政府が進める2020年のパワハラ防止の法制化。タイミングを図ったかのように)
人手不足を補うべく、新卒採用や中途採用を行なっても全然人が来ないし、採用できたとしても、その大変さからスグに辞めてしまう。
補充どころか、今いる従業員が辞めてしまうと事業の継続すら困難になりそうだと、心配に心配が輪をかけて押し寄せてくるというお困りごと。
そしてさらに、2020年4月からの同一労働同一賃金。
中小企業には猶予期間があるとはいえ、パート社員に頼ってたところはその処遇改善を考えると頭が痛くなることばかりです。
中小企業で特によく聞く悩み事です。
働き方改革に対応できる体力のない会社は、経済成長の妨げになるので淘汰される? 衰退産業から成長産業への労働者移動を政策目標の一つに掲げる安倍政権の本意は、どうやらここにありそうです。
大手広告代理・電通での痛ましい不幸な事件が政府の進める働き方改革の重なり、また、ブラック企業を根絶すべきという世論の高まりを好機に、一気に法改正へと突き進んでいったわけです。
しかし、現状はというと、事件当事者である電通の責任問題はどこか遠くの話になってしまい、かわりに先の中小零細企業の厳しい経営危機の問題の方がジワジワ大きくなっているように感じます。
働き方改革に対応できないところ、人材が集まらない、定着しない、そういうところは社会的必要性がないので、吸収か、合併か、または消滅かと、国の主導の施策でじわじわと追い込んでいる、そんな意図を感じます。
中小企業だけでなく、大企業の足元も盤石とは言えない状況です。
たとえば、金融ビジネスにおいては、IT企業やベンチャー企業の参入で、誰もが不動の立場にあると思っていた銀行の存在イメージがガラリと変わってしまったり、日本の主力産業である自動車関連企業の経営統合や合併も頻繁となり、金融業界同様、うかうかしていると外資IT企業の下請産業に成り下がる可能性だって十分にありえます。
政府主導の働き方改革とSociety5.0によるデジタルイノベーションで、中長期的に成長できる企業かどうか、その選別を行い、生き残れない企業は自然淘汰もやむなし。
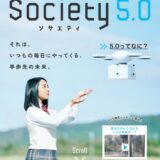 Society5.0 の認知度と対応って、どーなの?
Society5.0 の認知度と対応って、どーなの?
少子化による労働人口が減ったぶん、DXやIoT,AIで業務バランスをとり、少ない企業・限られた人材でも最大の成果を産み出す、効率的な産業システムへの改変。
それが、経済成長を第一に考える政府の成長戦略の根底にあるのではないかと思います。
政府主導で進める働き方改革の最終到着点は、労働力を必要なところへ柔軟にスピーディーに移動できる仕組みでしょう。 成長産業は常に変化し、その変化のスピードも増していくはずです。
となると、必要なのは、その変化に対応できる人材を活用する仕組み作りが急務です。
米国O-NETに倣って、日本でも国が運営する職業情報提供サイト(日本版O-NET)を立ち上げることが構想としてあります。
 日本版O-NETってナニ?
日本版O-NETってナニ?
転職希望者の就職活動と企業の採用活動をマッチングさせるわけですが、コレはもはや政府が積極的に転職を促すことを宣言しているようなものです。
ひとつのところでキャリアを停滞させるのではなく、多様なキャリアの効果的な活用でイノベーションを創出することが、競争力の強化につながると。
政府主導で進む「大転職時代」がもうすぐそこに来ているのです。
2020年4月の同一労働同一賃金なども、そのための土壌づくりのひとつとも考えられます。
ハローワークも来年早々から求人システムを変更するようですし。
 ハローワークの求人・求職サービス「ハローワークインターネットサービス」が徐々にレベルアップしています
ハローワークの求人・求職サービス「ハローワークインターネットサービス」が徐々にレベルアップしています
また、話題になった新卒採用における就職情報企業R社のAIで内定辞退予測云々の例の問題が、民間主体の就職システムから政府主導の就職システムへ移行する転機になったりするかもしれません。
 「リクナビの内定辞退をAIで予測」について思うこと
「リクナビの内定辞退をAIで予測」について思うこと
この日本版O-NET、優先順位を上げて、スピード感をもって実現すべきだと思います。
なかなか浸透してはいないですが、厚生労働省には「ジョブ・カード制度」という発想がるわけですから、それをアレンジし、システム化して。
適切なシステムのもと、本人の自由な意志で転職できる環境が整備されれば、ブラック企業は存続できなくなるはずです。
また、ハラスメントの横行する理不尽な職場で、生活のためになんとか我慢して働く必要もなくなるはずです。
もちろん、働く人の意識改革も必要になります。
自社で必要なスキルと、どこでも必要なスキルのバランス感覚。
会社任せのキャリア形成からの脱却。
ポータブル・スキルの修得とバージョン・アップ。
なんだか大変そうにも思われますが、本当の意味での自己実現が可能になるわけですので、働きがいも向上すると期待できます。
企業も個人も停滞から変化への変革が必要な時代へ突入です。 変化に対応できる人が生きがいを得られる時代に間違いなく向かっています。
「進化論」を提唱したダーウィンは言っています。
最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのでもない。
唯一生き残るのは、変化できるものである。
ダーウィン
これを好機と見て備えるか、危機と怯えるか、ですね。