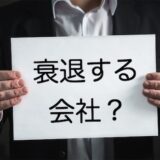こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。
厚生労働省のホームページにも記載のとおり、国が進める働き方改革の柱は、長時間労働の削減です。
長時間労働削減に向けた取組
「我が国においては依然として長時間労働が問題となっており、長時間労働の削減は喫緊の課題です。これに取り組むため、「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけや、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の徹底等を行っています。」
長時間労働は、社員の健康を脅かすリスクであることはいうまでもなく、社員の安全配慮義務の責任を担う企業にとっても大きな経営リスクです。
また、従業員の健康管理という観点から生産性の向上を図る「健康経営」が重要視されています。
少子高齢化により、今後ますます労働人口が減っていき、採用が困難となる日本において、従業員が健康的に、やりがいをもって長く働ける職場づくりに取り組むことは、経営戦略上とても重要なことであり、そのような安心感と働きがいの共存する魅力ある職場には自然と有能な人材が集まってきます。
逆に、長時間労働を放置し、従業員の心身の健康を蝕むような働き方を強いる企業は、社会悪というレッテルを貼られしまい、淘汰されてしまいます。
企業としての存続や永続において、今や「働く職場の環境づくり」は「人づくり」と同じぐらい重要な位置付けにあります。
こうした背景も手伝い、働き方改革の目的に長時間労働の削減を掲げているところが多いです。
先に示した国の方針に基づく労働基準監督署からの指導により取り組まざるを得ないところも含めて。
長時間労働を削減するには、現状の仕事量を減らさないのであれば「人を増やす」、現状の人の数を増やさないのであれば「仕事量を減らす」ということになります。
当たり前の原理です。しかし、いずれもの場合も一時的に利益が減ってしまいます。
短期的な数値を重視する経営層には受け入れがたい施策でしょう。
そこで出てくる解決策が「生産性の向上」です。
仕事のボリュームを減らすことなく、今のままの人員で、業務の効率化を図り、労働時間を削減しようというもの。
確かに、公益財団法人 日本生産性本部の労働生産性の国際比較データを見ての通り、日本の労働生産性が先進国の中でかなり低いことがわかります。
http://jpc-net1.sb-bmobilized.com
時間当たりの労働生産性も低いです。このデータから、労働生産性の高い他国に比べると、密度も集中力もアウトプット(成果)も低い仕事をしていると評価されます。
もちろん日本人の皆がそうというわけではなく、組織によっても、個人によってもその差はあるものの、総じて平均的に「仕事の仕方」に改善の余地があるということです。
生産性の向上の鍵は、管理職のマネジメント能力
仕事の仕方の改善に取り組むということは、部下がどのように仕事をしているのか、そこに問題があるのかないのか、問題があればどのように改善していくのか、アウトプット(成果)と同じぐらいプロセス(過程)を適正にマネジメントすることが重要になります。
これにより、そもそも受注している業務量は適正か、適正な人員体制か、業務フローは適正かなど、4M(ムリ・ムラ・ムダ・ムボウ)が明らかになります。
これまで、数値(結果)だけで業務と部下を管理していた管理職は、マネジメントについての意識を大きく変えなくてはなりません。
もちろんメンバーにもこの意識変革が強く求められるわけですが、働き方改革を成果に繋げるためには、まずは経営トップのしっかりとした方針のもと、経営層・管理職層が共通の認識をもって現場の指揮にあたることが必須です。
働き方改革の取り組み目標を、単に残業禁止、時間外労働は月○時間までとし、それに対して管理職がプロセスのマネジメントをせずに結果だけを管理したら、不満足な働き方により従業員のモチベーションは下がる一方です。
もちろん、生産性に好影響は及びません。
肩書きだけの管理職かそうでないか、そこに企業の未来がかかっています。