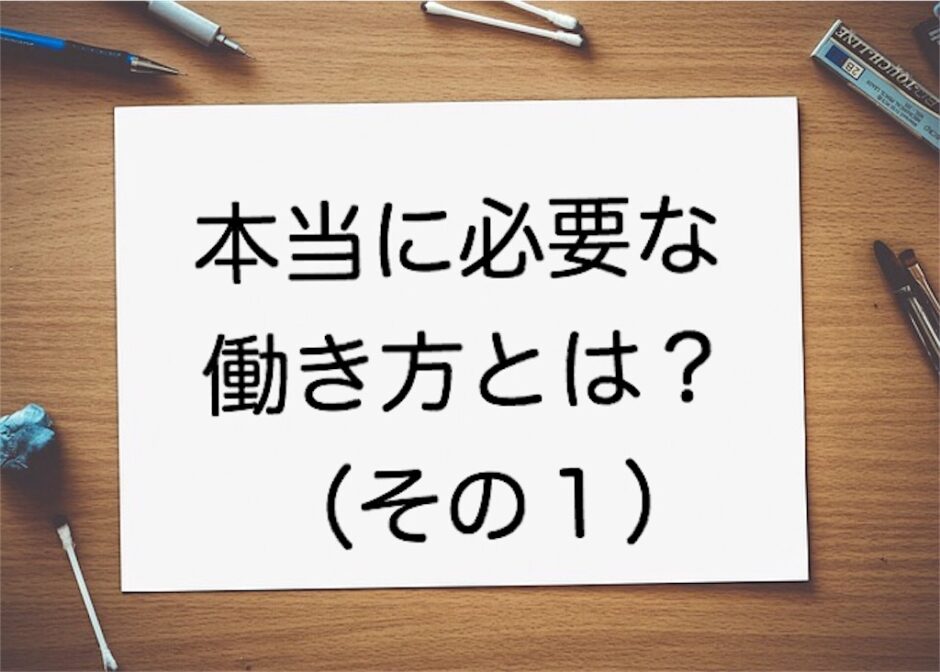こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。
言うまでもないことですが、「働く」とは、生きていくためのひとつの手段であり、多くの人の場合、好む好まないは別として、働かざるをえない状況にあるわけです。
生活が成り立つのであれば、もちろん働かないという選択肢もあるわけですが。
いずれにしても、まずは、働くことのベースにある「どう生きるか」についてを考えることが重要です。
ただ、この「どう生きるか」といった生き方ついての思想は、生涯不変であり続ける必要もなく、自分を取り巻く状況や変化に応じて柔軟に見直すことの方がむしろ一般的です。
そして、この「どう生きるか」と「どう働くか」についての個々人の権利(義務)を明らかにしているのが皆さんがよく知っているアレです。
日本国憲法です。
この憲法をベースに、あらためて本来のあるべき姿を検証し、イノベーティブな時代の働き方についてを考えてみます。
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
誰もが生まれながらにして基本的な人権を持っていて、それは、誰からも侵されることのない永久的なものだとしています。(享有→生まれながらにして持っていること)
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
他人に迷惑をかけない限り、生きるとこ、自由であること、幸せになることは、政治や法律などで最大限に尊重されるべきものだとしています。
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
そして、差別のない平等な社会を目指しているわけで、当然に職業や有職・無職、正規・非正規など雇用の形態での差別もありえないのです。
しかし、ここの表現は古いですね。
「等」といった例示の列挙ではなく、すごく限定的です。
例えば、門地(家柄)も重要ですが、それよりも「LGBT」のような、いまどきの世界標準的なテーマを取り上げることが大事ではないでしょうか?
第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
人に迷惑をかけない限り、どんな仕事に就くかは個人の自由ですし、退職・転職にも当然に制限も制約もありません。
第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
誰もが健康で人間らしい最低限の生活をする権利があり、国は社会福祉とか社会保障で国民の生活を向上させるために、このようにハッキリと「努力義務」が課せられているのです。
第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
すべての国民には、働くことに対しての権利と義務があるとしています。
そして、二項には、いきなり勤務条件の具体的内容と、それを法律で定める「労働基準法」が登場するので、勤労のためには労働者になることが絶対的のような印象を受けてしまいます。
これは、ニートや専業主婦は違法なのか?とよく議論されることですが、当然、ニートや専業主婦のように無職だからといって罰せられるものではありません。
この「義務を負う」は、戦後の日本の経済復興には国民全員の労働参加が必要不可欠という、時代背景(国の都合)から記述されているように思われます。
これは「一億総活躍社会」の実現を掲げる今の安倍政権のご都合にも近いように感じます。
また、気になるのが「勤労の義務」の部分。
勤労という言葉の意味には「心身を労して仕事にはげむこと」があります。(引用:goo国語辞書)
心身を労するまで働くことが国民の義務であるとすると、過労死を容認しているように受け取れますし、ワーク・ライフ・バランスどころではないです。
以上、今回は、働くということに関し、どう生きるかに関係の深い「日本国憲法」について教養のひとつとして見てみました。
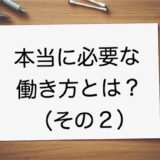 本当の働き方改革とは何か? 日本国憲法の基本を踏まえ、イノベーティブな時代に求められる働き方のあるべき姿とは?(2/3)
本当の働き方改革とは何か? 日本国憲法の基本を踏まえ、イノベーティブな時代に求められる働き方のあるべき姿とは?(2/3)