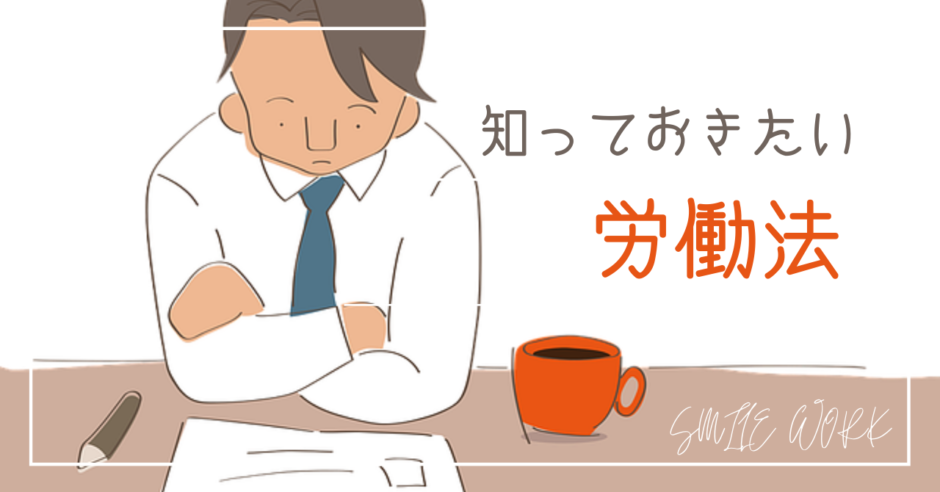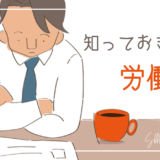こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。
今回は、働くうえで知っておきたい教養として「労働法の基本(労働基準法)」について解説します。
2019年4月から働き方改革関連の法律改正が段階的に行われました。
改正の目玉は、やはり「時間外労働の罰則付き上限規制の導入」。
今回は、その「労働時間」というものが、法律ではどのように定められているのかを確認しておきたいと思います。
これは社員に限らず、パート・アルバイト(学生も)・派遣など、働くすべての人に適用される働く上での基本であり、大事なルールです。
労働時間については、1週間および1日の最長時間が労働基準法によって決められています。(法律で決められた時間なので「法定労働時間」と呼びます。)
第32条(労働時間)
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
40時間を超えてとあるように、40時間ちょうどは問題ありませんが、厳密に言うと、40時間を1分でも超えると法律上ではアウトです。
これを「1週40時間制」とも言います。
また、1週間の各日については、休憩時間を除いて8時間を超えて労働させてはならないと定めています。
「1日8時間制」とも言われています。
例えば、始業9時00分、休憩12時00分から13時00分(1時間)、終業18時00分で1日の労働時間が8時間、週休2日制により1週間の労働日数5日、5日×8時間=40時間としている企業が多いのは、この法定労働時間の遵守が背景にあるわけです。
本来は、1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えて労働させると法律違反なのです。
では、残業や休日勤務というのは法律違反なのでしょうか?
労働基準法では、法定労働時間を超えて労働させるためのルールに従い使用者と労働者で手続き(労使協定と言います)をすれば、可能であるとも規定しています。
これが労働基準法の36条に定められていますので、この手続きのことを「36(サブロク)協定」と呼んだりしています。
2019年4月の法改正により、この36協定の手続き内容も変わりました。
言いかえると、この36協定の手続きが適正にされていないと、使用者は労働者に法定労働時間を超えて労働させることはできないのです。
ただし、労働者側にも注意が必要です。法定労働時間を超えて働く(残業する)場合、会社(上司)の許可なく勝手にやってはダメ!というルールを就業規則に規定しているところが珍しくありません。
これに従わずに勝手に残業するとルール違反(服務規律違反など)を問われることがあります。
就業規則はきちんと確認しましょうね。