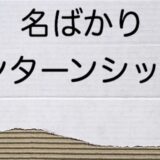こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。
ネット、メール、チャット、ツイッター、フェイスブック、ライン、インスタ…
IT技術の進展によりビジネスにおけるコミュニケーションのあり方も変化しています。
しかし、意外とその必要性が変わらないのが「ビジネスフォン(会社の固定電話)」です。
使用頻度こそ減ってはいますが「大事な話はメールではなく電話で」というのは、今も変わりありません。
良いか悪いかは別として。
実は、この電話の応対で「仕事ができる人」「できないが人」が分かります。
まず、電話が長い人は仕事ができない、というのは世界共通の評価です。
まわりくどい表現で、結論が何なのか、ただ長い、という人。
あなたの周りにもいませんか?
さらに、その長い電話を「私は一生懸命に仕事してんだぞ!」的なアピールで、したり顔の人も。
相手の貴重な時間を奪っている意識もありません。
とても残念な人です。
役職や立場をステイタスとしているタイプの人に多いです。
他に電話応対ができる人がいないのに、鳴っている電話に出ない人。
放ったらかし。
さらに最悪なのは「おーい!電話が鳴ってるぞ。
早く出ないと!」と探しに…。
電話は女性や部下が出るもので、私の仕事ではない!と、電話応対を軽く考えている人。
こういう人に限って部下のビジネスマナーにうるさかったりします。
仕事のチャンスは一本の電話から、とさえ言われます。
良くも悪くも、電話応対ひとつで状況が一転してしまうのです。電話は会話そのものだけでなく、鳴ってから切るまでがコミュニケーション(テレコミュニケーション・スキル)です。
これも電話を取らない人に近いです。
たいして忙しくもないのに、たとえ大事な用件であっても部下や女性社員に代わりに電話をかけさせる上司。
電話をかける?そんなことは部下の仕事で、私の役割じゃない!と…
ひょっとして相手はその件について、その上司本人からの電話であれば話したい、と思っていたかもしれません。
ちょとした事が、印象を悪くしたり、ビジネスの機会損失に繋がることもあります。
そういう上司に限って「なんであの会社、取引を断ってきたんだ? きちんと原因究明をしておけよ」と騒いだり…。後の祭りです。
見えない相手との会話による電話は、その人のコミュニケーション能力のレベルが顕著にあらわれます。
まず、相手の声の調子や様子などから、相手の状況を素早く察知し、臨機応変な態度対応がとれるか。
正確にスピードよく、効率の良いコミュニケーションが図れるか。
そのためには、しっかり聞き、メモをとり、確認をする。
社会人として相応しい言葉遣いは、言うまでも基本中の基本です。ダラダラと、結果何が言いたかったのか分からない電話は、相手の大事な時間を浪費させるだけでなく、周囲をも不愉快にさせます。
「待たせず、丁寧に、大切に応対する」が、テレコミュニケーション・スキルの基本。
上司が率先して実践し、そうした職場の雰囲気を作りあげることが大事です。
「お客様第一」を「率先垂範」。
そうした姿勢は、確実に部下に伝わります。
・できる人は、電話の重要さを知っています。
・できる人は、電話応対を大切にします。
・できる人は、自分の都合優先で、相手の時間を奪うツールが電話であるということを十分理解したうえで活用しています。
就活生向けのセミナーや、新人のビジネスマナー研修などで、電話対応について、いまもしつこくやってます。
電話というものが存在する限り、大事なコミュニケーション・ツールですので。
はじめは、ケータイ・スマホとビジネス電話の違いから。
若い人にはかなりカルチャーショックみたいですね、固定電話に出ることは。
まずはそこからのチャレンジです。