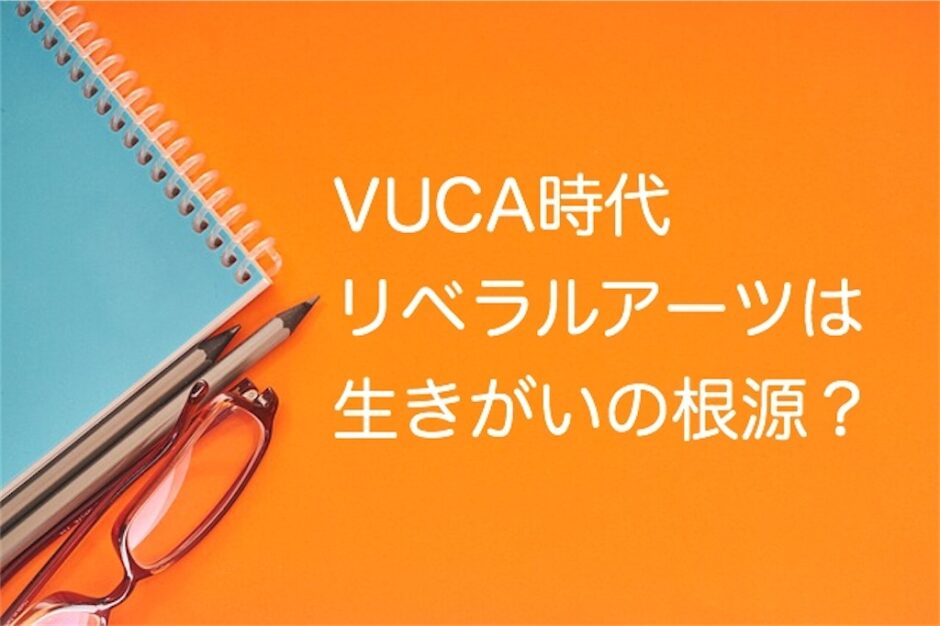こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。
先の見えない不透明な時代にこそ
これから先、何が起きるか分からない「未来」の不確実さに、ワクワク感を抱く人がいれば、不安感に苛まれる人もいます。
変化や変革を歓迎し、その波に乗ってしまえ!的な人と、刺激的な人生より安定した生活を望む人など、受けとめ方は人それぞれです。
もちろん、「生き方」には、正解やあるべき模範もありませんので、どれが良いとか悪いということではありません。
その「未来」の様子が少しずつ変わってきているように感じています。
皆さんはどうですか?
VUCA時代を生きる
「未来に確実性はない」とは言うものの、これまでは、誰もがある程度、なんとなくでも想像できる大きな枠の範囲の中で、未来に向かってゆっくり進んでいたように思えます。
ある程度、想定した範囲内で。
ところが、ここ数年は「VUCA時代」とも言われているように「何が起きるのか分からない、先が見えない」が前提の時代に突入したことを感じることばかりです。
政治、経済、国際情勢、技術、自然などありとあらゆる分野で・・・。
一見すると、表面的には変化を感じないことであっても、その根っこの部分では、超加速的にかつ変態的に、複雑多様化の変化が進んでいたりもしますし。
ちなみに VUCA(ブカ、ブーカ)とは
- Volatility(変動性)
- Uncertainty(不確実性)
- Complexity(複雑性)
- Ambiguity(曖昧性)
近頃はビジネスの現場でよく使われている用語ですが、もともとはアメリカの軍事用語が起源です。
何が起きるのか予測が困難な時代をどう生きるか、どう働くか。
カオスな現代社会の中で「〜らしく生きる」には、どうすればいいのでしょうか?
教養がモノを言う時代
VUCA時代を「〜らしく生きる」には、アレコレと自分で思考を巡らし、いくつかの仮説を立て、自らの意志で決断しやってみることが重要になります。
そして、その繰り返しの中で、自分なりの正解を導き出す論理を確立していくのです。
このプロセスの精度を高めるための重要な手がかりになるのが「教養」です。
表面的なスキルは、時代の変化により陳腐化することもありますが、「教養」は “生き抜く知恵と創造力の源” になります。
ここでいう「教養」とは、単に広く知識を習得することではありません。
「教養=リベラルアーツ」とするのが相応しいでしょう。
リベラルアーツとは?
古代ギリシャ時代の「人を自由にする学問」が根源であり、その具体的内容は、文法・修辞・弁証、算術・幾何・天文・音楽で、これらを「自由七科」と呼んでいます。
奴隷から脱却し自由を手に入れる術としての教養に、その後、神学と哲学が加わり、学問の基礎を築いてきたわけですが、重要なポイントはこの「哲学」にあると思います。
自分としての哲学
幅広い分野についての確かな知識(視野の広さ)に、哲学的なモノの見方(視座の高さ)と、諦めることなくトコトン考え抜く骨太な思考力とが密に関係し合うことで、自分としての意見と考えを持ち続けることができるようになります。(ブレない自分、自分らしさ)
そして、すべての教養の基礎となるのが「哲学」であるとも言えます。
“ 社会(会社)の奴隷にならず、自分らしく自由に生きていくために、多様な知識や価値観に触れながら、自分の思考で探求するクセを身に付けることが極めて重要です。”
グローバル人材の育成のために英語の授業を導入し、英語の会話はできるようになるかもしれませんが、創造的な議論ができるでしょうか?(異国の文化、価値観の違いこそがコミュニケーションのベースでは?)
IT人材の育成のためにプログラムの授業を導入し、プログラミングの作業はできるようになるかもしれませんが、イノベーティブなシステムを創出することができるでしょうか?
英語もプログラミングも役に立たないわけではありませんが、AIやIoT、ロボットなどにとって変わりうるテクニカルな教育よりも、英会話より外国の文化や歴史(=価値観の違い)、プログラミングよりもアルゴリズム(論理的思考)など、本質的で普遍的な能力の向上を目指すべきではないかと思います。
できれば、小中学校などの早い時期から「哲学」を中心にしっかり「リベラルアーツ(教養)」に慣れ親しむ機会を増やしてはどうかと。
自分はいったい何者?
生きるってどういうことか?
なぜ、働かないといけないの?
なぜ、いじめはいけないのか?
といった、正解のないことについて考えたり、自分なりの意見を述べるとなると、そのことについての確かな知識が必要になりますし、価値観の違いを理解することの必要性と、人とのリアルな関係作りの大事さを知るきっかけにもなると思います。
みんな違う、自分と他人は違う、違って良いんだと。
これこそが教育の現場で取り組んでいる「アクティブ・ラーニング」の原点ではないかとも思います。
AI時代、グローバル社会など、どんな環境でも、どんな変化にでも対応できる「地頭力(自分で考え抜く力)」が鍛えられるはずです。