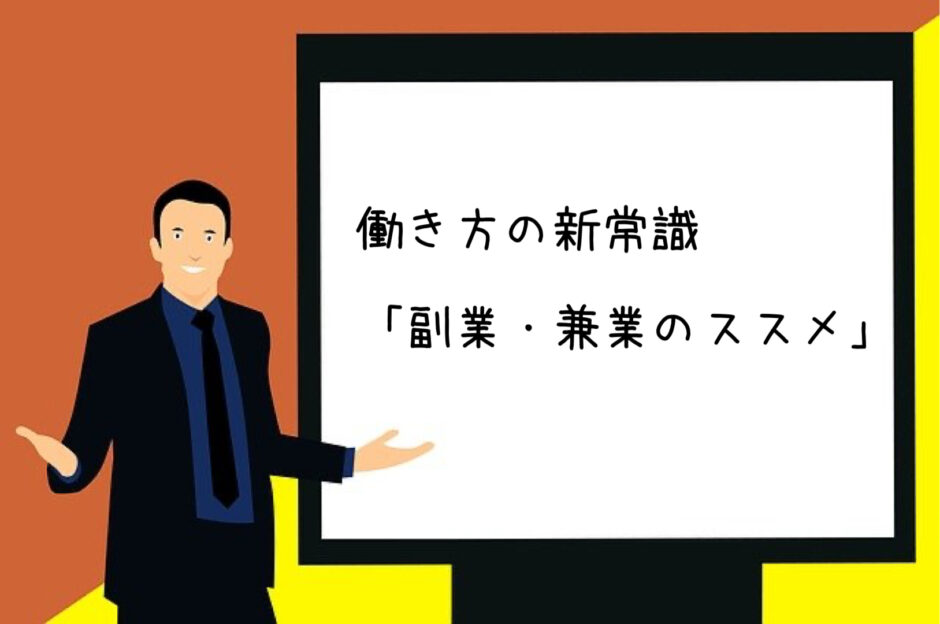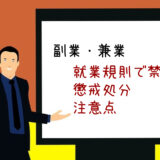こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。
今回は、何かと話題の「副業・兼業」についての話。
オープンイノベーションを引き起こすネクスト・ワークの鍵
社会通念上のワーク・ルールが劇的に変わり、働き方の考え方も大きく変わりつつあります。
ひとつの会社で働き尽くす(滅私奉公?)ことが当然であったこれまでの雇用慣行において副業・兼業は否定的であり、二重就職として禁止又は厳しく制限されるのが当然だと考えられてきました。
その副業・兼業がオープンイノベーション(企業の成長・従業員の成長)を引き起こすネクストワークの鍵であるとして原則自由になったのです。
これも政府が進める「働き方改革」の一環です。
労働のルールを管轄する厚生労働省のホームページでは以下のとおり副業・兼業についての考え方がハッキリ明記されています。
これからの働くを考える上で大事なポイント(国策・政府のメッセージ)がまとめられています。
ぜひご一読ください。
厚生労働省では、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っています。
厚生労働省公式サイト https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
厚生労働省(政府)は企業に対し、副業・兼業を認めるように強く働きかけています。
これからの雇用に関する日本政府の大方針です。
これは、働く側(労働者)に対しても副業・兼業を念頭に置いたキャリア形成や生活スタイルの確立を促しているわけです。
これからの「働く」とは、従来の古典的で画一的な労働ではなく、多様な働き方を前提としたマルチスキルとキャリアチェンジが当たり前であるという発想の転換期。
そして、「副業・兼業の促進に関するガイドライン 平成30年1月策定(令和2年9月改定)」を公表し、企業と労働者に対してその必要性と意義を明確にかつ具体的に定義しています。
このガイドラインの中からポイントとなる要旨を抜粋し厚生労働省(国)の言わんとする事をひも解いてみます。
1 副業・兼業の現状
(1) 副業・兼業を希望する者は年々増加傾向にある。副業・兼業を行う理由は、収入を増やしたい、1つの仕事だけでは生活できない、自分が活躍できる場を広げる、様々な分野の人とつながりができる、時間のゆとりがある、現在の仕事で必要な能力を活用・向上させる等さまざまであり、また、副業・兼業の形態も、 正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまである。
(2) 副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは、例えば、
1 労務提供上の支障がある場合
2 業務上の秘密が漏洩する場合
3 競業により自社の利益が害される場合
4 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
に該当する場合と解されている。
(3) 厚生労働省が平成30年1月に改定したモデル就業規則においても、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」とされている。
副業・兼業の促進に関するガイドライン(厚生労働省)
まず、注目すべきは1-(1) の副業・兼業を行う理由の上位に「収入が少なく今の仕事だけでは生活できない」という労働者がいると素直に公言していること。
その解決策として「副業・兼業」を押しているという現実。
そして 1-(2) の副業・兼業に関する裁判例に関する箇所。
「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由」であると、これまでの原則禁止から一転、原則自由へ「副業・兼業」の考え方がガラッと変わりました。
これにより、多くの企業がこれまで就業規則などで副業・兼業を禁止又は許可制にしていたルールについて否定するものであり、1〜4に該当する事由を除いて、禁止又は制限できるものではないとしています。
さらに、厚生労働省のモデル就業規則についてもガイドラインの(3)に記載の通り「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」と改められています。
副業・兼業の"促進"とは思えない、かなり"強行的"なガイドラインになっています。
そのための理由づけ(企業と労働者のメリット)と留意点もガイドライン「副業・兼業の促進の方向性」に具体的に記載されています。
2 副業・兼業の促進の方向性
(1) 副業・兼業は、労働者と企業それぞれにメリットと留意すべき点がある。
【労働者】
メリット:
1 離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、労働者が主体的にキャリアを形成することができる。
2 本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求することができる。
3 所得が増加する。
4 本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた準備・試行ができる。
留意点:
1 就業時間が長くなる可能性があるため、労働者自身による就業時間や健康の管理も一定程度必要である。
2 職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要である。
3 1週間の所定労働時間が短い業務を複数行う場合には、雇用保険等の適用がない場合があることに留意が必要である。
【企業】
メリット:
1 労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。
2 労働者の自律性・自主性を促すことができる。
3 優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。
4 労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。
留意点:
1 必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応が必要である。
・・・略・・・
(2) 人生100年時代を迎え、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境を作っていくことが必要である。また、副業・兼業は、社会全体としてみれば、 オープンイノベーションや起業の手段としても有効であり、都市部の人材を地方でも活かすという観点から地方創生にも資する面もあると考えられる。
(3) これらを踏まえると、労働者が副業・兼業を行う理由は、収入を増やしたい、 1つの仕事だけでは生活できない、自分が活躍できる場を広げる等さまざまであり、業種や職種によって仕事の内容、収入等も様々な実情があるが、自身の能力を一企業にとらわれずに幅広く発揮したい、スキルアップを図りたいなどの希望を持つ労働者がいることから、こうした労働者については、長時間労働、企業への労務提供上の支障や業務上の秘密の漏洩等を招かないよう留意しつつ、雇用されない働き方も含め、その希望に応じて幅広く副業・兼業を行える環境を整備することが重要である。
また、いずれの形態の副業・兼業においても、労働者の心身の健康の確保、ゆとりある生活の実現の観点から法定労働時間が定められている趣旨にも鑑み、長時間労働にならないよう、以下の3〜5に留意して行われることが必要である。
・・・略・・・
4 なお、労働基準法(以下「労基法」という。)の労働時間規制、労働安全衛生法の安全衛生規制等を潜脱するような形態や、合理的な理由なく労働条件等を労働者の不利益に変更するような形態で行われる副業・兼業は、認められず、 違法な偽装請負の場合や、請負であるかのような契約としているが実態は雇用契約だと認められる場合等においては、就労の実態に応じて、労基法、労働安全衛生法等における使用者責任が問われる。
副業・兼業の促進に関するガイドライン(厚生労働省)
副業・兼業を禁止又は一律許可制にしている企業については労働者の希望に応じて副業・兼業を認める方向で検討するように、ガイドライン「企業の対応」にはこれからの働き方について基本的な考え方を具体的に明示しています。
ただ、このような考えを法制化したルールなどは労働基準法に存在しません。
これは労働法のレベルではなく、その上位に位置する日本国憲法第(13条・第22条)によるものとし、留意事項として明確にしています。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
副業・兼業は、個人の私生活上の自由と職業選択の自由を保障するものということです。
企業(使用者)と個人(労働者)との労働契約は、あくまでも労働契約及び就業規則に定める所定の就業日、所定の就業時間について労務提供と対価としての賃金支払いを約束するものであり、労働契約を締結したからといって企業は24時間・365日労働者を拘束できるものではありません。
したがって、私生活において他の職に就くことなどは本来自由であり、特別な理由がない限りそれを不当に制限することは個人の人権を侵害する行為となり得るということです。
副業・兼業を認めないことは場合によっては人権問題であると、厚生労働省は判例(裁判例)を用いて企業にこの事を強く知らしめているといるわけです。
※ 公務員は国家公務員法・地方公務員法により副業が禁止されています。したがって、副業を希望する場合には必ず許可が必要になります。
3 企業の対応
(1) 基本的な考え方
裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。 副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかを今一度精査したうえで、そのような事情がなければ、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求められる。
実際に副業・兼業を進めるに当たっては、労働者と企業の双方が納得感を持って進めることができるよう、企業と労働者との間で十分にコミュニケーションをとることが重要である。なお、副業・兼業に係る相談、自己申告等を行ったことにより不利益な取扱いをすることはできない。
また、労働契約法第3条第4項において、「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。」とされている(信義誠実の原則)。信義誠実の原則に基づき、使用者及び労働者は、労働契約上の主たる義務(使用者の賃金支払義務、労働者の労務提供義務)のほかに、多様な付随義務を負っている。
副業・兼業の場合には、以下の点に留意する必要がある。
副業・兼業の禁止又は制限
(ア) 副業・兼業に関する裁判例においては、
・ 労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であること
・ 例外的に、労働者の副業・兼業を禁止又は制限することができるとされた場合としては
1 労務提供上の支障がある場合
2 業務上の秘密が漏洩する場合
3 競業により自社の利益が害される場合
4 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合が認められている。
このため、就業規則において、
・ 原則として、労働者は副業・兼業を行うことができること
・ 例外的に、上記1〜4のいずれかに該当する場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくこと等が考えられる。
(イ) なお、副業・兼業に関する裁判例においては、就業規則において労働者が副業・兼業を行う際に許可等の手続を求め、これへの違反を懲戒事由としている場合において、形式的に就業規則の規定に抵触したとしても、職場秩序に影響せず、使用者に対する労務提供に支障を生ぜしめない程度・態様のものは、禁止違反に当たらないとし、懲戒処分を認めていない。
このため、労働者の副業・兼業が形式的に就業規則の規定に抵触する場合であっても、懲戒処分を行うか否かについては、職場秩序に影響が及んだか否か等の実質的な要素を考慮した上で、あくまでも慎重に判断することが考えられる。
副業・兼業の促進に関するガイドライン(厚生労働省)
副業・兼業の考え方は政府の具体的な方針提示によりこのように劇的に変わっています。
そして、企業・従業員双方の競争力強化のためのイノベーションを画策し、いち早く副業・兼業を促進する制度を設け実践している副業解禁の事例も出てきています。
その一方で、副業・兼業を変わらずネガティブにとらえ、そのまま原則禁止をルールとしている経営者もいます。
従業員にチャレンジを要求し、チャレンジの環境を創出できない経営者のもとでイノベーションは起きません。
今後この発想の違いは、企業間格差を拡大させるわけです。
政府が推進する「働き方改革」とは、次世代に生き残り躍進する企業とそうでない企業との選別がその目的でもあるといえます。
毎年のように施行される労働法令の改正にきちんと対応できるかどうか。
法令遵守のできないブラック企業はもちろん、政府の掲げる方針に対応できない(しない)企業、成長の見込めない企業(衰退企業)は社会から退場を余儀なくされるという厳しい選別。
副業・兼業などのオープンイノベーションを引き起こすためのネクスト・ワークを積極的に取り入れながらスピード感のある経営判断のできる経営者か、そうでない(残念な)経営者か。
経営者の能力、力量が試される時代です。
これは、働く側として自社の将来予測をする上でとても重要なポイントです。