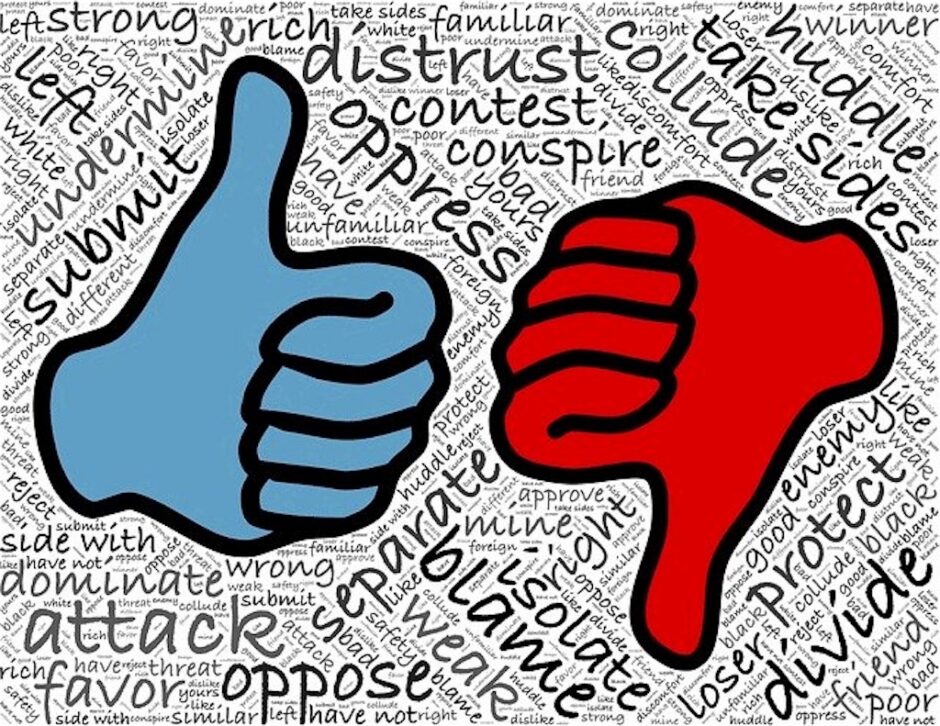こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。
2019年4月の労働基準法改正は、日本の労働慣行にとって大きな転機を迎える、そんな節目になりそうです。
今回の法改正は、労働者の幸福を実現するための働き方改革というより、安倍政権が成果目標として掲げる経済成長のための働かせ方改革が目的になっているのは誰もが承知のことかと思います。
安倍政権が描く経済成長シナリオにある脆弱部分を働き方改革で補うわけです。
安倍政権にとっての働き方改革とは、目的ではなく、目標達成のためのひとつの手段にすぎないという理解が必要です。働く側にとっては。
すべての企業において、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、1年以内に5日間の取得を義務化します。
それも罰則付きで。有給休暇の取得率が低いから、取りにくいから、強制取得で取得率を上げるわけです。
もしその企業に勤める労働者が1人でも年5日の取得ができなかったら法違反になります。
コンプライアンス経営が当たり前に問われる現在、もしも法違反で処罰となれば、炎上必至でブラック企業の仲間入りに…。
来年4月1日からの施行に向け、労使による確実な実行のためのルールづくりはとても重要です。
そして、その確実な実行のための施策として、多くの企業が検討しているのが「有給休暇の計画的付与制度」の導入です。
制度の導入には労使協定の締結が必要となりますが、導入すると、△月△日は有給休暇を付与し一斉に休みとします(事業所別、班別、個人別で)とすることが可能になります。
以前からこの制度は存在するのですが、今回の法改正の対策として、かなりの企業が導入に踏み切るのではないかと思われます。
5日間のすべてを一斉にするのか、5日以内の日数に限定するのか、それは労使の話し合いによります。
また、一斉に有給付与で休む日をいつにするかも労使の話し合いで決まります。
もちろん、その対象となるすべての労働者は、個人の都合は関係なく、その決められた日は休まないといけません。
こうして付与された有給休暇も今回の法改正による5日の取得義務にカウントできることになっています。
簡単に言うと、年間勤務カレンダーにあらかじめ有給休暇の取得日が指定されるわけです。
有給休暇の取得率の上昇が働き方改革の成果と目論む政府(安倍政権)の都合に、本来なら労働者にとって自由な権利である有給休暇の権利が奪われる構図になってしまうのです。
有給休暇の5日と一部ではあるものの、インパクトはやはり大きいです。
労働者の権利であり、自由であるはずの有給休暇を、法律で強制し、無理ムリにでも休ませるわけですから。
もちろん労働者にとって有給で確実に休めるということは嬉しいことです。
でも、その嬉しいはずのことまで法律で強制するということに強く違和感を感じています。
なにか、派遣法や年金法のように、その当事者にとってプラスになるはずで始まったことがいつのまにかマイナスに作用したという同じ改悪の道を歩んでいくのではないかと危惧しています。