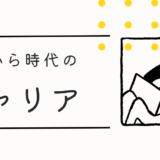こんにちは、Gene-K(@SmileWork_LAB)です。
同じ仕事でも、一緒に仕事をする人や職場の環境によって、モチベーション(やる気)が変わってしまうことはよくあることです。誰と、どういう環境で仕事をするのかは、とても大事な要素です。
例えば、就職(転職)や異動先が、自律的ではなく「やらされ感」で仕事をしている人たちが多い職場だった、ということは、決して珍しいことではありません。
こうした職場を作り出す要因は、どこにあるのでしょうか。また、そのような職場環境の中で自分自身は、どのようにキャリア形成(成長)していったらいいのでしょうか。
今回は、そのあたりの話に触れてみたいと思います。
「やらされ感」で仕事をしている人たちが多い職場を作り出す要因
従業員が自律的に考動するのではなく、日々なんとなく「やらされ感」で仕事をしている人たちが多い職場を作り出す要因はどこにあるのでしょうか。
いくつかの要因が考えられますが、最も多いのが経営陣の問題です。その典型的な問題例を挙げてみます。
コミュニケーションの欠如
経営陣が従業員との適切なコミュニケーションを怠っている場合、従業員は仕事への動機づけを得にくくなります。指示やフィードバックが不明確であったり、必要な情報が共有されなかったりすることが問題の根底にあります。
役割や責任の不明確さ
経営陣が方針を明確にし、それを実現するためのミッションを定めない場合、従業員が自分の役割や責任を明確に理解できず、仕事に対する自己成就感や意欲が低下します。明確な目標や期待が示されないまま、単調な作業を繰り返すことで「やらされ感」が一般化します。
従業員のスキルや能力の不足
経営陣が従業員のスキルや能力を適切に評価し、必要なトレーニングやサポートを提供しない場合、従業員は職務遂行能力に対して自信を持てず、モチベーションが低下します。その結果、その能力の範囲の仕事に終始し、「やらされ感」が生じる可能性があります。
評価と処遇の問題
経営陣が従業員の活躍ぶりを適切に評価し処遇しない場合、新たな仕事へのチャレンジ、スキルや能力の向上、自分の担当外の仕事を行うことは無駄であると、損得勘定で仕事をとらえる傾向があります。その結果、評価と処遇の範囲の仕事以外に興味を示さず「やらされ感」が生じやすくなります。
働き方の文化や環境の問題
経営陣が適切な労働環境(多様な働き方)と従業員の健康に対する興味が低い場合、長時間労働や過度の業務負荷、無理な期限設定など、働き方の文化や環境がストレスや疲弊を引き起こし、従業員は仕事に対して前向きな姿勢を維持することが難しくなります。
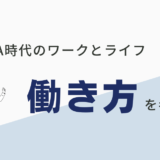 これからの働き方に関する大事な話 〜 政府が進める新しい資本主義実現会議で論じられている、あんなこと・こんなこと 〜
これからの働き方に関する大事な話 〜 政府が進める新しい資本主義実現会議で論じられている、あんなこと・こんなこと 〜
これらの要因が組み合わさることで、やっても無駄、むしろ余計なことはしない方が得策という思考に陥り、「やらされ感」が蔓延する職場環境が形成されるということはよくあることです。
こうしたことが昨今では重要な経営課題と認識され、エンゲージメント経営、健康経営、さらには人的資本経営と取りざたされている背景でもありす。
経営陣はこれらの経営課題に対して真剣に取り組み、従業員の意欲や能力を引き出し、自律的に価値を生み出す組織文化にするための様々な施策(モチベーション・マネジメント等)を考える必要があります。
 会社の見方:人的資本経営、エンゲージメント、心理的安全性と言われる今の時代の企業経営において重要なこととは?
会社の見方:人的資本経営、エンゲージメント、心理的安全性と言われる今の時代の企業経営において重要なこととは?
「やらされ感」ではなく自律的に働くには
「やらされ感」で仕事をしている人たちが多い職場であっても、自分自身の仕事に対する思考と行動をコントロールすることで、自律的に働く能力と習慣を高めることが可能です。
自分の仕事の目的や意義を理解する
どんな仕事にも行う目的や意義があります(あるはずです)。自分の仕事の目的や意義を理解することで、仕事に対するモチベーションが上がり、自律的に行動することができるようになります。また、なぜこの仕事をしているのか、自分の仕事が会社の全体にどのような貢献をしているのか、ということを理解することで、自分の仕事の重要性を認識することができます。また、自分の仕事の目的や意義を理解することで、仕事に取り組む際に、より大きな視点を持って取り組むことができるようになります。
自分の仕事の目標や課題を明確にする
自分の仕事の目標や課題を明確にすることで、それに向けて自分の行動を計画し、実行することができます。目標や課題が明確であれば、自分の仕事に取り組む際に、より具体的な行動目標を立てることができます。また、目標や課題が明確であれば、自分の仕事の進捗状況を把握し、必要に応じて軌道修正をすることができます。
自分の仕事に対するフィードバックを受ける
自分の仕事に対するフィードバックを受けることによって、自分の仕事の強みや弱み、改善点などを知ることができます。フィードバックを受けて改善することで、より自律的に仕事ができるようになります。また、フィードバックを受けることによって、自分の仕事に対するモチベーションが上がり、より積極的に仕事に取り組むことができるようになります。
自分の仕事に責任を持つ
前の3項目の実施により、自分の仕事に対する必要性と責任が明らかになります。自分の仕事に責任を持つことで、仕事に対するモチベーションが上がり、自律的に行動することができるようになります。自分の仕事に責任を持つためには、自分の仕事の目標や課題を明確にする必要があります。また、自分の仕事の進捗状況を把握し、必要に応じて軌道修正をする必要があります。さらに、自分の仕事の成果を評価し、必要に応じて改善する必要があります。
やらされ感で仕事をするのではなく、自律的に考動するためには、これらのことを意識することが大切です。
「やらされ感」の職場環境でのキャリア形成
これからの時代、会社任せ、他人任せのキャリア形成ではなく、個人を主体としたキャリア形成へと大きく転換していくと思われます。政府の示す新しい資本主義にもその方向性が明確に表現されています。
「リ・スキリングによる能力向上支援」については、現在、企業経由が中心となっている在職者への学び直し支援策について、5年以内を目途に、効果を検証しつつ、過半が個人経由での給付が可能となるよう、個人への直接支援を拡充する。
経済財政運営と改革の基本方針 2023
 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023改訂版案 の概要
新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023改訂版案 の概要
「やらされ感」で仕事をしている職場環境であるか否かを問わず、周囲に流されず、自分主導でキャリアキャリア形成を実現することが、自分らしさとやりがいを育みます。そのために、以下のようなアプローチを考えることが重要です。
目標設定と計画
キャリアの方向性を明確にし、中長期的な目標を設定しましょう。その後、その目標を達成するための具体的な計画を立てます。必要なスキルや経験、教育やトレーニングの取得方法についても検討しましょう。
スキルの習得と成長
キャリア形成に必要なスキルを積極的に習得しましょう。自己学習、トレーニングプログラム、セミナーやワークショップへの参加など、さまざまな手段を活用して自己成長を図ります。また、上司やメンターからのフィードバックを受けることも大切です。
挑戦と貢献
新しいプロジェクトや任務に積極的に関わり、自身のスキルや能力を試す機会を作りましょう。さらに、周囲の人々や組織に貢献することを意識し、自身のアイデアや提案を積極的に発信します。
ネットワーキング
業界や関連分野のプロフェッショナルとの関係を築くことが重要です。業界イベントやセミナーに参加し、他の専門家とのつながりを作りましょう。また、自分の興味や専門分野に関連するオンラインコミュニティやソーシャルメディアのグループに参加することも有益です。
メンターシップと助言
経験豊富な人や上司からのメンターシップや助言を受けることは非常に有益です。自分の成長に関するフィードバックやキャリアのアドバイスを求め、相談することで、自身の進歩を促すことができます。
これらのアプローチを継続的に取り組みながら、自己啓発とキャリア形成に取り組みましょう。また、自身の関心や価値観に合った職場やプロジェクトを選ぶことも重要です。
また、残念ながら、勤め先の経営陣が従業員のキャリア形成に全く興味がない場合もあります。経営陣が従業員のキャリア形成に興味を示さない場合でも、自身のキャリア形成に取り組むことは可能です。以下にいくつかのアイデアをご紹介します。
自己評価と目標設定
自身のスキル、強み、興味、目標を客観的に評価しましょう。自分自身に対して明確な目標を設定し、それに向かって進む計画を立てます。
自己学習
インターネットや書籍、オンラインコースなどを活用して、自己学習を行いましょう。自分が興味を持つ分野やキャリアに関連するスキルや知識を独自に習得することができます。
アウトサイドネットワーキング
組織外の人々とのネットワーキングを積極的に行いましょう。業界のイベントやコミュニティに参加し、他の専門家や同じ志を持つ人々とのつながりを作ります。彼らからのフィードバックやアドバイスは非常に価値があります。
副業やボランティア活動
自分の興味やスキルに関連する副業やボランティア活動に参加することで、新たな経験を積むことができます。これにより、自己成長や新たなスキルの習得、他の組織や人々とのつながりを築くことができます。
転職やキャリアチェンジの検討
現在の職場がキャリア形成に適さない場合、転職やキャリアチェンジを検討することも考えましょう。自身の成長やキャリア目標に合致する環境を求めることは重要です。
 不足し続ける日本のIT人材。就職・転職・副業・起業・学び直しで、飛躍の一歩を踏み出す
不足し続ける日本のIT人材。就職・転職・副業・起業・学び直しで、飛躍の一歩を踏み出す
自己のキャリア形成に取り組む際には、自己主導性、継続的な学習、目標志向性が重要です。外部のリソースや機会を活用し、自身の成長とキャリアの進展に向けて努力を続けてください。